宮川輝子 ― 温故知新の精神が紡ぐ、未来への物語

「温故知新」という言葉は、しばしば先人の知恵を尊び、過去から学ぶ意味で使われる。しかし、宮川輝子さんの歩みを聞けば、その言葉には「過去を未来へとつなぎ、新たな価値を創造する」という、より能動的な意味が込められていることに気づかされる。彼女の人生は、失われかけた記憶に再び光を当て、次の世代へと継承するための、静かで、しかし確固たる意志に満ちた旅路のようだ。彼女が語る言葉の端々には、過去への敬意と、未来への深い眼差しが宿っている。それは、まるで時を編み直すかのように、一人の人間の記憶が、やがて社会全体の歴史となっていく過程を物語っている。
幼少期・学生時代や原点
宮川輝子さんは、幼い頃から活発で、好奇心旺盛な少女だった。いわゆる「女の子らしい」とされる遊びよりも、男の子たちと外を駆け回り、自由に泥まみれになることを好んだという。その奔放で、固定観念にとらわれない気質は、彼女の人生の大きな原点となっている。特に印象的なのは、苦手なことへの向き合い方だ。学生時代、編み物が大の苦手で、母親に手伝ってもらってようやく靴下を完成させたという。その出来栄えを見て、宮川さんは「やればできる」という小さな達成感を胸に刻んだ。さらに、環境運動に携わるようになった際には、文章を書くという、やはり苦手だった作業に直面する。しかし、社会のために声を上げる必要性から、嘆願書や声明文を何度も書き直し、ついにその苦手意識を克服した。これらの経験は、彼女が目の前の困難を乗り越えるたびに、自己の可能性を広げていくという、後の人生を貫く姿勢へと繋がっていく。
「文章を書くことが苦手でした。でも、やらなきゃいけない環境に置かれると、できるようになるものなんですね。私は、何かを『好き』でやるよりも、『やらなきゃいけない』と思ってやる方が、うまくいくみたいです。」
この言葉は、宮川さんが単なる「努力家」ではなく、強い使命感を持って行動する人間であることを示唆している。個人的な好き嫌いを超え、社会的な要請や責任を原動力に変えることができる彼女の強さが、この初期の経験で育まれた。そして、その達成感が、新たな挑戦へと踏み出す勇気を与え続けている。

夢や転機
多感な時期、宮川さんには音楽の道に進むという確固たる夢があった。しかし、その才能と情熱は、厳格な母親の「あんたみたいな気性の激しい子が音楽家になってもしょうがない」という言葉によって、断念せざるを得なくなった。夢を絶たれたことは、若き宮川さんにとって大きな挫折であったに違いない。しかし、この一見ネガティブな出来事は、彼女の人生に大きな転機をもたらす。母親の勧めで進んだ社会福祉学科での学びが、彼女の人生観に深く影響を与え、社会全体を俯瞰する広い視野を養うことになったのだ。そこで出会った、それぞれの専門分野で活躍する優秀な教授陣との交流は、彼女の知的好奇心を刺激し、単なる夢の代替ではなく、自身の人生を豊かにする新たな道を見つけるきっかけとなった。
「母の言ったことは全部正しかったんだなと、今になって思います。あの時、もし音楽の道に進んでいたら、今の私はなかったでしょうから。」
若き日の挫折を、今では人生を形作った必然として受け入れている宮川さん。この言葉からは、過去の出来事に対する深い洞察と、自身の選択に対する確固たる肯定感が伝わってくる。社会福祉という道を選んだことが、後の会社経営や人との関わりにおいて、収益だけではない「人の幸せ」という普遍的な価値を追求する揺るぎない信念となった。
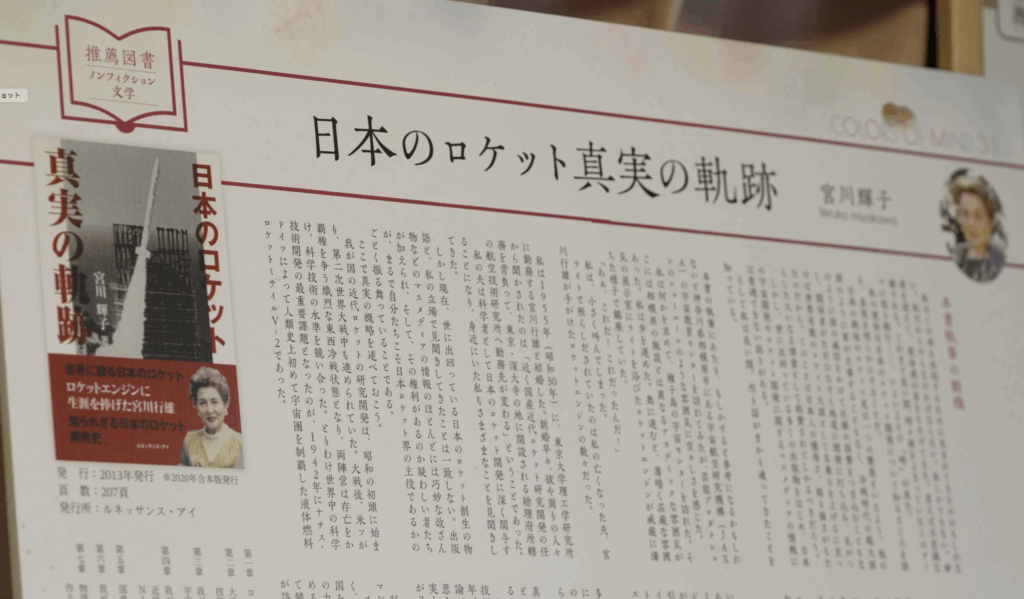
活動や理念
宮川さんは、自身の会社を単なる収益を追求する組織とは考えていない。「社会を明るく元気にする会社」という理念を掲げ、社員一人ひとりの人生を豊かにすることを目標にしている。その象徴が、毎朝の朝礼だ。そこでは、彼女自身の言葉で社員に語りかけ、個々のモチベーションを高め、会社全体の一体感を育んでいる。彼女にとって会社経営とは、社員の人生を預かる責任を伴う、いわば社会福祉活動の一環なのだ。この哲学は、社会福祉学科での学びが深く根付いていることを物語っている。
「会社は、社員の人生を豊かにする場所でなければならない。社員の人生を預かるという気持ちで経営しています。だから、社員には自分の人生を好きになってもらいたいし、そのための環境を整えるのが私の役目だと考えています。」
この言葉は、宮川さんの経営哲学が、単なるビジネス論ではなく、人間性に基づいたものであることを明確に示している。社員の幸福を第一に考えることで、結果的に会社全体の生産性や社会貢献度が向上するという、持続可能な経営モデルを実践している。彼女のリーダーシップは、社員に安心感と未来への希望を与え、会社を単なる職場以上の存在へと高めている。

技術・道具・挑戦
宮川さんの挑戦は、決して過去の遺産に安住するものではない。約30年前、まだ一般的ではなかったパソコンに、彼女はいち早く興味を持ち、独学で習得した。新しいもの好きだった父親の影響も大きかったという。彼女は、パソコンを単なる流行と捉えるのではなく、自身の活動や事業をより良くするための「道具」として積極的に活用した。会社経営にパソコンを導入し、経営状況をデータ化することで、それまで感覚に頼っていた部分を客観的に把握できるようになった。これにより、より正確で迅速な経営判断が可能となり、会社の成長に大きく貢献した。
「会社の状態を感覚ではなく、データという客観的な情報で把握することで、正確な判断ができるようになりました。技術は、私たちをより良い未来へと導くためのツールだと信じています。」
このエピソードは、宮川さんが伝統を重んじつつも、常に新しい技術や可能性に対して開かれた姿勢を持っていることを示している。彼女にとって、技術は過去の経験と融合し、より強固な基盤を築くための手段なのだ。この柔軟な発想と行動力が、彼女の挑戦の歴史を支え、時代の一歩先を行く存在たらしめている。
現在の活動と信念
宮川さんの信念は、今も日々の実践の中に深く息づいている。特に、タンスに眠る着物に関する彼女の言葉は、その哲学を象徴している。着物を「かわいそう」に思う気持ちから、日常的に着物を着るようになったというエピソードは、単なる物の話ではない。それは、過去の文化や歴史、そしてそれらに込められた人々の想いを大切にし、再び光を当てるという、彼女の「温故知新」の精神が、日常生活にまで浸透していることを示している。彼女は、古いものにこそ、時代を超えて伝わる普遍的な価値があると考えている。
「タンスにしまったままの着物って、かわいそうじゃないですか。ちゃんと日の目を見せてあげたいなって思って。古いものには、たくさんの人の思いが詰まっているから、それを次の世代に繋いでいきたいんです。」
この言葉は、宮川さんが単に過去を懐かしむのではなく、未来への責任感を持って、文化や記憶を継承しようとしていることを示している。彼女の活動は、物質的な遺産だけでなく、それに込められた精神的な価値をも掘り起こし、現代に生きる私たちに、改めて「残す」ことの重要性を問いかけている。

残すという選択。ARTRELICとの出会い
「これまで私は、“その場で感じてもらえれば十分”と思っていました。記録に残すことよりも、目の前の人との対話を大切にしていましたから。」
宮川さんは、自身の活動や哲学を多くの人に伝えることの重要性を感じてはいたものの、その記録を体系的に残すことには無頓着だった。しかし、ARTRELICで「未来に残す」という視点に触れたことで、その考えは大きく変わった。インタビュー動画や対談記録をアーカイブとして未来に残すことは、単なる記録以上の意味を持つことを理解したのだ。自身の言葉や思考プロセスをデジタルデータとして保存することは、次世代が彼女の哲学を学び、新しい価値を創造するための貴重な「遺物」となる。ARTRELICは、彼女がこれまで歩んできた道のりと、その道のりを照らしてきた哲学を、未来の光へと変えるための重要な役割を担っている。
活動をもっと知るには?
- ▶ ポートフォリオサイトURL
- ▶ 展示記録URL
- ▶ Instagram URL

まとめ:静かな余白に、心が映る
宮川さんの活動は、決して派手なパフォーマンスや強い説得力に頼るものではない。むしろ、彼女が大切にしているのは、作品や言葉の間に生まれる「余白」や、完璧ではない「揺らぎ」だ。それは、鑑賞者が自身の心を投影し、内なる声に耳を傾けるための静かな空間となる。過去を敬い、現在を慈しみ、未来へと静かに想いを紡いでいくその姿勢は、彼女の活動そのものが、やがて「未来に残されていく記憶の層」となることを示している。そして、その層に触れた私たちは、自身の心に静かな余白が生まれ、そこに宿るべき未来の姿を映し出すことができるのかもしれない。




この記事へのコメントはありません。